訓練・講話(起震車・煙体験、訓練実施計画書もココ)
ページ番号:917537687
更新日:2025年6月20日
自治会・町会等の地域住民の方が防災訓練を行う際は、防災危機管理課や地域の消防署に事前申し込みをする必要があります。マンション等の集合住宅、保育園・幼稚園・学校・福祉施設・企業・グループ単位での防災訓練や防災講話も受け付けております。
下記をご参考のうえ、不明点は防災危機管理課(電話:03-5744-1611)までお問い合わせください。
大田区が指導する主な訓練等
- 地震体験車(起震車)による地震時の初期対応訓練
- 煙体験ハウスによる火災時の避難訓練
- 防災講話(防災危機管理課職員による)
- 訓練用資機材の貸し出し(炊き出し用のかまどや防災に関するDVDなど)
大田区が指導する訓練の申し込み方法
申し込みは大田区内の団体等に限ります。
1 地震体験車(起震車)、煙体験訓練の予約(抽選の実施)
抽選実施日:訓練月の6か月前の、月初めの平日午前9時
(例:11月に訓練を希望する場合・・5月の月初めの平日に実施します)
(予約不可日:毎週金曜日、大田区総合防災訓練の実施日、年末年始等
利用時間:原則として午前9時30分から11時30分、午後1時30分から3時まで
詳しくはお電話にてお問い合わせください)
抽選方法:防災危機管理課の職員による抽選
(注釈1)複数の職員立ち会いのもと、厳正に抽選を実施いたします。
抽選終了後、(9時30分から)順次お電話で予約を受け付けています。
(訓練月の前月10日までに、お申し込みください)
抽選またはお電話で予約後、
「訓練実施計画書」を防災危機管理課または地域の特別出張所へご提出ください。
(FAXも可。訓練月の前月10日までに、ご提出をお願いします)
![]() ★「訓練実施計画書」のダウンロード画面へ(Word:52KB)
★「訓練実施計画書」のダウンロード画面へ(Word:52KB)
地震体験車(起震車)訓練における留意事項
(1)訓練時は、十分なスペースを確保できていること。
【地震体験車(起震車)】
全長:614cm
全幅:250cm (訓練時 425cm)
全高:282cm (訓練時 357cm)
重さ:7t
(2)雨天時は実施できない。
(3)地震体験車(起震車)の進入口・設置場所が平坦であること。
(4)地震体験車(起震車)の訓練場所の地面が軟弱で補強する場合は、要請者側で行うこと。
煙体験訓練における留意事項
(1)普通車の駐車スペースがあること。
【煙体験ハウス】
全長:360cm
全幅:180cm
全高:180cm
(2)雨天時は実施できない。
地震体験車(起震車)
煙体験ハウス
2 訓練周知ポスター・チラシの配布
防災訓練に一人でも多くの方が参加していただけるよう、訓練周知用のポスターを配布しています。下記からダウンロードのうえ、ご使用ください。
防災危機管理課または地域の特別出張所で受け取りを希望される場合は、
「訓練実施計画書」に必要部数を記入・提出後、受取希望日を事前連絡のうえ、窓口へお越しください。
(1)地域用ポスター
地域の掲示板などに掲出して、地域の方の参加を呼びかけるものです。
(2)訓練周知用回覧チラシ
町会の回覧板等に挟んで、防災訓練の実施を周知するものです。
地域用ポスター
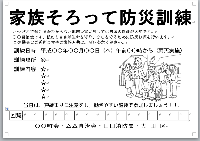
訓練周知用回覧チラシ
3 試食用備蓄食糧等の配布
避難所などに備蓄してある食糧で、消費期限が近くなったものを試食用として防災訓練時に配布しています。
(消費期限が近いため、保存せずすぐに召し上がってください)
必要数・届け先を「訓練実施計画書」に記入のうえ、
防災危機管理課または地域の特別出張所へご提出ください。
(必ず訓練月の前月10日までに、ご提出をお願いします)。
試食用区備蓄食糧等
- クラッカー 1箱70人分
- レトルト(カレーライス、ケチャップライス、中華丼) 1箱30人分
4 防災セミナー・講話
区では、下記防災講座を行っております。ぜひご利用ください。
・「どこでもおおた防災セミナー」
申込団体が希望する日時・場所に防災専門家を派遣し講座を行います。
講話内容は「風水害編」と「震災編」の2種類から選択できます。
詳細は下記をご覧ください!
出前講座「どこでもおおた防災セミナー」「小・中学生向けおおた防災教室」【受付中!】
・防災危機管理課職員による防災講話
時間、場所、講話内容等について直接防災危機管理課までご相談ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京都では、防災の専門家が下記防災講座を行っております。こちらもご利用ください。
・「東京防災学習セミナー」
地域の自主防災組織や町会・マンション管理組合等に防災の専門家を派遣するセミナーです。
東京マイ・タイムラインの作成や、マンション防災についてのコースもあるので
ぜひ下記からお申込みください。
・「パパママ東京ぼうさい出前教室」
子育て世代のグループが気軽に防災の知識や備えを学ぶことができるよう、
親子防災に詳しい専門家を派遣する講座です。
災害から子供を守るための防災知識や備えを学べるので、ぜひ下記からお申込みください。
![]() 令和7年度「パパママ東京ぼうさい出前教室」募集開始!(外部リンク)
令和7年度「パパママ東京ぼうさい出前教室」募集開始!(外部リンク)
消防署が指導する主な訓練等
- 煙体験ハウスによる火災時の避難訓練
- 初期消火訓練
- 応急救護訓練(三角巾・AED取り扱い訓練)
- 通報訓練(119番への電話のかけ方)
- 救出、救助訓練(倒壊家屋からの救出方法)
- 家具転倒防止措置の説明
- 住宅用火災警報器の説明
- 消火隊・ミニポンプ隊操法訓練
- スタンドパイプ操法訓練
消防署が指導する訓練の申し込み方法
事前に地域の消防署に申し込みをしてください。
消防署へ申し込み後、「訓練実施計画書」を防災危機管理課または地域の特別出張所へ提出してください。

写真:初期消火訓練

写真:救出、救助訓練
主な防災訓練一覧
| 訓練項目 | 内容 | 指導申込先 |
|---|---|---|
| 起震車 | 起震車で地震の揺れを再現し、身の安全の取り方などを訓練します。 | 大田区 |
| 煙体験 | 煙体験ハウスの中に、火災時を想定した煙を充満させ、その中で安全に避難する方法を訓練します。 | 大田区または消防署 |
| 初期消火訓練 | 水消火器や街頭設置消火器、バケツ等を利用して消火訓練を行います。 | 消防署 |
| 応急救護訓練 | 三角巾による止血法、AED(自動体外式除細動器)を使用した心肺蘇生法など、様々な応急救護訓練を行います。 | 消防署 |
| 通報訓練 | 119番通報の要領を訓練します。 | 消防署 |
| 救出救助訓練 | がれきや柱などにより逃げることができない人を救出するための要領等を訓練します。 | 消防署 |
| 市民消火隊の訓練 | ミニポンプやC級ポンプ、スタンドパイプを使用した放水訓練を行います。 | 消防署 |
問い合わせ先
防災危機管理課
普及担当 (電話:03-5744-1611、FAX:03-5744-1519)
消防署
大森 (電話:03-3766-0119)
田園調布 (電話:03-3727-0119)
蒲田 (電話:03-3735-0119)
矢口 (電話:03-3758-0119)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
電話:03-5744-1611
FAX :03-5744-1519
メールによるお問い合わせ




